アナログ+必要最小限の信号の話
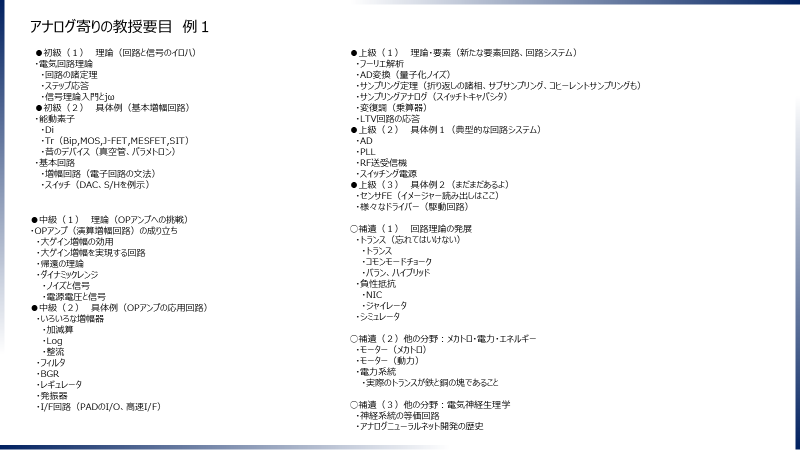
・電池と豆電球レベルから「回路」の話を始める。
・「電線を信号が伝わる」話が中心。これだけで回路と物理(電磁気)と信号の話ができる
・ここでTXとRXの概念を提示する(★シラバスの工夫点)
・この先、新しい概念を導入するたびに、TX~伝送路~RXという基本構成に立ち返り、課題がどのように見えてどのように解決されていくのか、そもそもTXとRXのどちらが大変なのかなどが、徐々にわかっていくとよい。
(「デジタル通信」導入直後はRXは単に閾値があるだけの簡単なものだが、そうは簡単にはいかないことを教えていけるとよい)
・R,L,C、電圧源、電流源の話は「回路の諸定理」に詰め込んでいる。「初級」のくくりはそこそこ重い。
・能動素子は不要。
・最初から三つ巴を大きく意識させてしまうのはMislead。ここは注意。
・線形な回路理論をほぼ語りつくしたら、「増幅したい」というモチベーションとともにトランジスタの話をする。
・基本的なデバイスの紹介において「物理」の方向を向くが、そこは早々に切り上げる。中級からは視線を「信号」へ誘い、「回路が信号処理をする」というイメージを早く作ってもらいたい。
・初級の段階でOPアンプの存在を前提にしないところで工夫ができる
・小振幅応答と大振幅動作の話を同時に行い、線形であるとみなせること自体すごいことであると言う
・大振幅応答の極限はSWかもしれない。
つまり、「Trなるものが発明されたが、どうやって使うか?」というお題からスタートし、典型的には3つ考えられる
1.増幅
2.スイッチ
3.乗算器
Diodeも同じことだったかもしれないが、増幅がちょっと怪しい※(負性抵抗で発信器を構成することしかできないのではないか?)
※「増幅作用」という用語があいまいかもしれない。いうならば「増幅回路を構成することができる作用(物理)」ならば「増幅作用」ということができるのであって、その作用の種類は問わない(電気でも光でも音でもよいのである)
・中級に「OPアンプ」を据えることの意義
OPアンプ単独商品のビジネスも存在するが、そのようなメーカーに属さない人でOPアンプを使ったり作ったりする人(=LSI搭載アナログ回路設計者)のほうが圧倒的に多いだろう。彼らには、高級なOPアンプの技というよりは、大ゲイン+高精度FBというユニバーサルな設計スタイルさえ知っていただければよい。実は、OPアンプ回路の作り方というのは回路システムをきちんと作るというための流儀に近いのではないか。OPアンプができるというのは、デジタルでいうと「Verilogコードをちゃんと書ける」というのに近い。