増幅器
・増幅器というと、真空管、半導体といった能動デバイスの専売特許に思われるかもしれないが、そんなことはない。
受動非線形素子でも可能。かつてパラメトロンが存在した。電話器で使われるカーボンマイクは、音声を増幅するといえる (百万人の電気技術史)
これは、電流が流れている可変抵抗(液体、濡れた紙、炭素編、炭素粒)を音声で変調するわけで、音声入力からすれば増幅動作が実現されたといえる。
現代的にはこれは「センサ」である。
・増幅器の等価回路として、複数の方法論が語られていることを知ってもらう
・ナレータ・ノレータモデル (能動素子の概念を言い換えただけで、「モデル」というほどでもないこと)
・2ポート等価回路
・gmRモデル (gmベースで回路を作りこんでいく手法)
・Hfeの税金モデル(加藤大@トラ技700号)
・帰還を伴う回路ならば、1+gmRx という因子がよく出てくる
・まずOPAmpなどで負帰還回路によく出てくる因子 1+βA を説明する。
・Trレベルの回路解析において、この因子がしょっちゅう出てくることを教える
1+gmRs ソースディジェネ
Ccb*(1+gmRs) (Rs: 信号源抵抗) よく覚えていないが、コレクタから見たインピーダンスの何かがRsでモジられるのを計算したことがある。
イメージセンサ
・完全電荷転送が重要だが、回路図だけでの表現が難しいこと
・PD→FD
・CCDの転送レジスタ
メモリ
・NV Tr
・FNトンネル電流(遅い)+Avalanche
・ホットエレクトロン注入
・MRAM、FeRAM
小回路機能
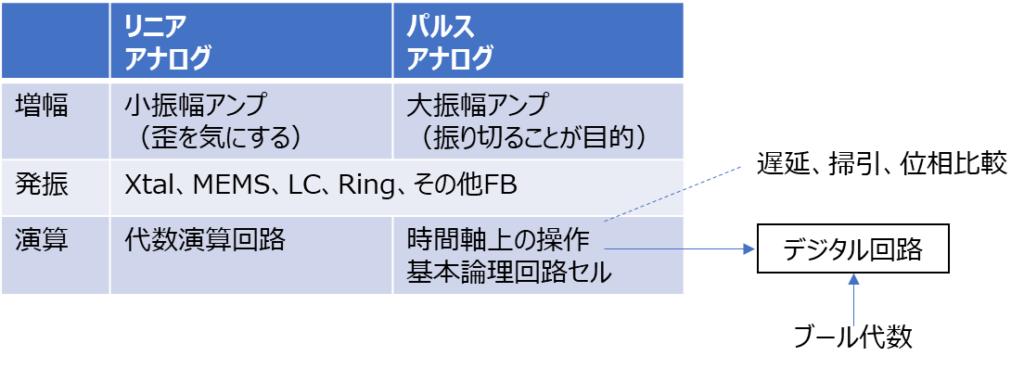
大回路システム
・共通 ADC、PLL (DACはその下のアンプと同じレベルでよい)
・信号伝送システム RFFE、I/F (信号伝送系)
・センサシステム
・ドライバシステム
→このシステムで語られる誤差がある。まずは「信号」と「ブロック図」で語られる
RF I/Qミスマッチ、LOリーク・・
PLL 位相ノイズ、各種ジッタ
ADC 量子化誤差、SFDR
センサ、ドライバは個々の用途でいろいろ
・技術階層の深さを考えるにあたって、「Trレベルの回路図とアーキテクチャ図の距離」を想像してみる。複雑度はずいぶん違うと思うが、RFはADC,PLLと同じぐらいか。
・ADCの諸方式の説明と、RF諸方式の説明は、ともに、基準時間(周波数)情報をもとに、信号に含まれる情報をキャプチャしようとしているので同等といえる。
・PLL一見異なるようにも思えるが、時間情報(REF)と、自分で作った入力(VCO出力)を比較していると考えれば、RF、ADCと似てくる。
→まとめると、アナログ要素(上位)の一般論としては、 “基準時間(周波数)情報に基づいて入力を加工して出力する“といえる
RF 周波数変換
ADC 量子化
PLL 位相誤差出力
・ある程度Trレベルの回路を知っている人に対しては、信号の話をした次に、この話をしてもよい ・増幅器のTrレベルの回路すら知らない人は、戸惑うだろう。ここをどのようにケアしていくか。