★中級で目指すところ
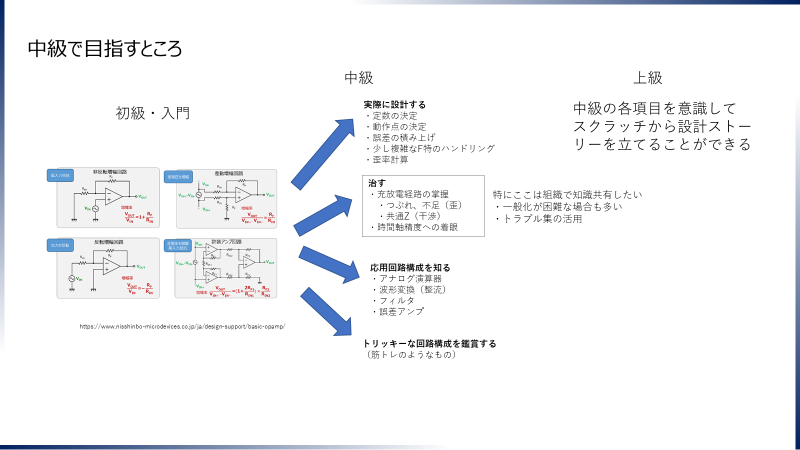
★なぜOPアンプを学ぶのか?
・電子回路はいろいろな学術の集大成。OPアンプはその縮図。OPアンプを学べば電子回路で必要な知識を一通り学べる
デバイス概論(モデリング)、回路理論、安定性理論、信号理論、歪、ノイズ、誤差、トラブルの様態
(そうなるように講座を設計する )
(オープンループが選好されたり、時間軸要素が強い回路など、OPアンプだけではカバーしきれない領域も明示しておく)
★OPアンプといってもピンキリだが、どこまで学ぶのか?
・初級 “OPアンプ設計においてシミュレーションができる” (回路は指示またはコピースタートで調整少し)
・回路図が作成できる(指示、参考資料活用)
・シミュレーションができる
・通り一遍の特性採取(DC、AC、TRAN)
・仕様項目に対するSim結果を明確にする
・条件振り
・定数調整ができる
・中級 “OPアンプを治せる”
・”治せる”ために、押さえておくべきOPアンプの特徴、着目点
・周波数帯域幅 DCからであること
・精度を追求するものであること(アナログコンピュータの話(下))
・特に、負荷駆動性の作りこみに注意することが必要
(GB積以外を理想のままシステム設計しないように)
・上級 シーケンス動作する回路の中でのOPアンプをとらえて、比較器、A/D変換器を語れるようにする。
・ADCへの道
・比較器として利用
・接続切り替えを伴う時間軸動作の導入
・そしてAD変換器
・上級補遺
・使いこなせる
・“新しいOPアンプの構成/OPアンプを使った回路を発明する”
(超ベテランに「ほう、そう来るか」と言われるレベル)
・AD変換を含む上位システムを設計できる
★知っておいたほうがよい:そもそも、なぜOPアンプが使われるのか
・回路のことあまり知らなくても使えるアナログコンピュータを作りたかった(「演算増幅器」と言われる所以)
・アナログ信号の加減算、定数倍、積分 → 線形微分方程式が解ける
・+乗算 → 非線形微分方程式にも道が開ける
・ミサイルの弾道計算に供することが期待されていた
・直流から使える、かつデバイスで決まるレベルに近い高速性(広帯域)が得られる
FBをかけて特性を制御するという点も2段階に分ける
1) ちょっとFBをかけてゲインを安定化する
2) アンプの素のゲインを必要なゲインとして使うのではなく、精度向上の原資として使い、必要ゲインは帰還率で決める
1)は、ただのアンプのころからも存在した(数値例でその効果を示したい)
2)はアナログ信号演算のニーズの出現で初めて認識されたコンセプトだと言ってよい(まず理屈だけできっちり説明し、数値は演習問題で)
★治すとはどういうことか
(ISO9001の「変更管理」に似ている)
・所望の動作・特性になるよう、構造、素子値を「変更」する。
・変更の影響の程度を、以下の変化で示す
・入出力仕様
・アーキテクチャ
・接続
・バイアス電流
・動作電位
・それでOKである理由を明確にする
・直接の要求事項がある場合
・「要求仕様xxxを満たす」
・直接の要求事項がない場合
・他の要求事項を材料に端的に論証する
★動作電位、バイアス電流関連の典型的な問い
・以下は、過渡応答、ばらつき含めて適切なマージン設計ができているか気にするときの問いだが、トラブルを見つけ出して「治す」のにも有用
・・Trが潰れてないですか?
・・Trの電流が枯れて無いですか?
・・TrがOffとなって帰還ループが切れてないですか?
★備忘
・治すためには的確な全体/部分動作理解が必要で、視点が複雑になる
・・ここを簡単にする方法はないものか
・・・ナレータ/ノレータモデルでどこまで使えるだろうか
・・・・開ループゲインが無くなった場合に使えるのか?